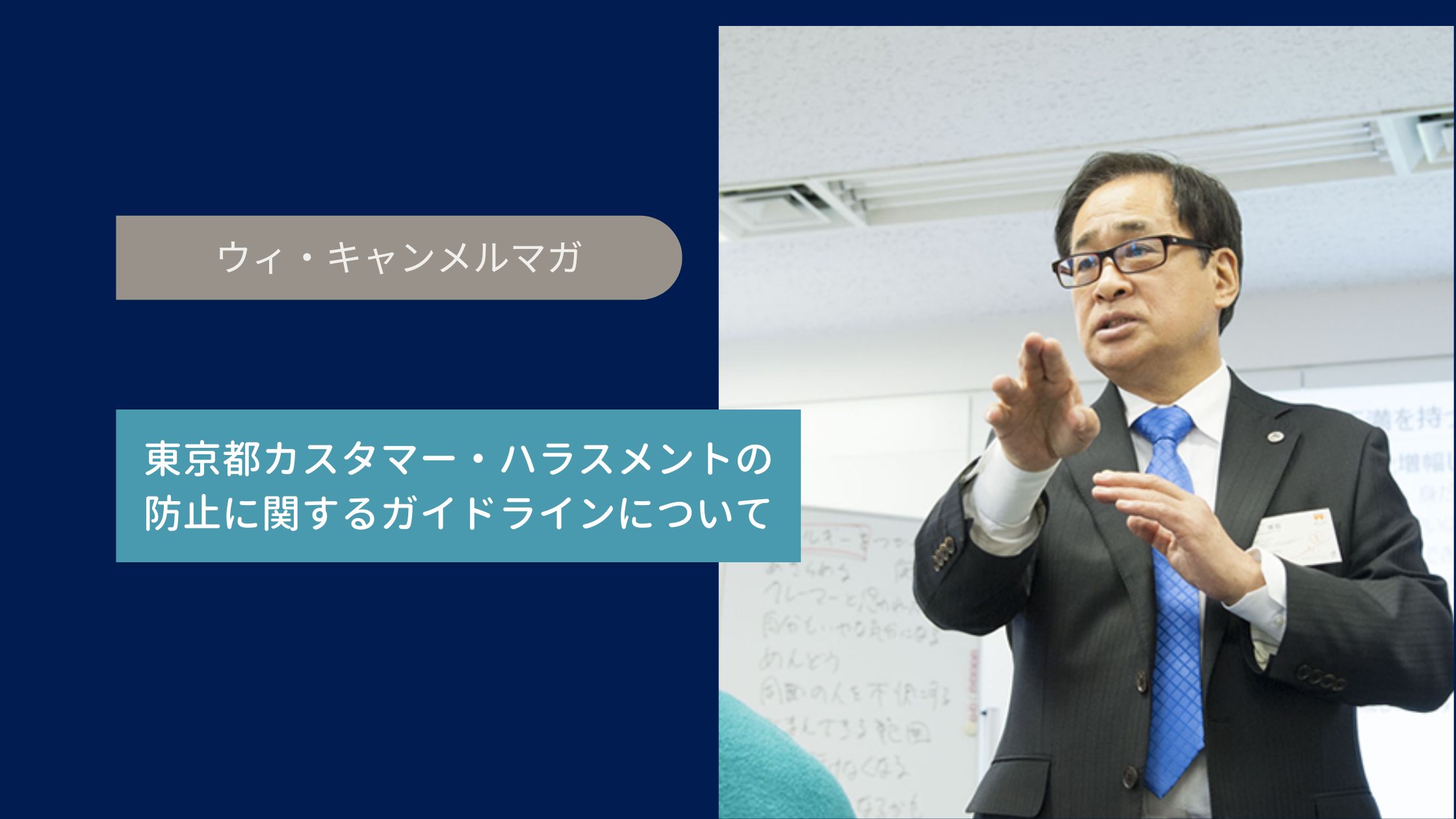はじめに
本年4月から、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」の具体的なガイドラインが発表されました。
医療・福祉業界で働く人たちにとっては、知っておかなければならない法令の一つだと考えます。
今回、ポイントをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
カスタマー・ハラスメントの内容
① 「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」
「何人も」とは、カスハラの行為主体となる人すべてを指し、都民に限定されません。また、個人だけでなく法人も含まれます。
「あらゆる場」とは、診察室や病院内の行為だけでなく、電話やインターネット等における行為も含まれます。
② カスハラの定義
【要件】
① 顧客等(患者、ご家族だけでなく本来は関りが想定されていない人であっても業務遂行上必要となった人も含む)から就業者に対する行為であること
② 当該業務に関して著しい迷惑行為であること
③ 就業環境を害するもの
以上、3要素を含むものが条例ではカスハラであると規定されています。
ここで注意することは、刑法との関係です。要素をすべて満たさない場合でも、「著しい迷惑行為」そのものは刑法等に基づき処罰の対象や、民法上の損害賠償の対象になる可能性があります。
③ 著しい迷惑行為
ア 暴行、脅迫その他違法な行為
暴行、脅迫、傷害、強要、名誉毀損、侮辱、威力業務妨害、不退去等の刑法上の規定する違法な行為のほか、ストーカー規制法や軽犯罪法等の特別刑法に規定する違法な行為
これらはカスハラの要件を満たしていなくとも犯罪になる可能性が高いと思われますので、このような行為を受けた場合は、警察に連絡することが大切です。
イ 正当な理由がない過度な要求
客観的に合理的な社会通念上相当と認められる理由がなく、要求内容は不当であるもの(巨額の損害賠償の請求や、疾病治療に関して常識範囲を離れた要求)や、大声をあげて秩序を乱すなど、行為の手段・態様が不相当であるもののことです。
「社会通念上相当と認められる」の判断基準について
大声を出せばすぐ「カスハラ」になるかは疑問です。
条例内には、「当該行為の目的、当該行為を受けた職員の問題行動の有無や内容・性質、当該行為の態様・頻度・継続性、就業者の心身の状況等の様々な要素を総合的に判断しなければならない」とあります。
例えば、診察室で会計の職員に「会計に計算違いがある!」と、大声で非難する患者がいます。
職員は委縮してしまい、おどおどするばかりです。
2~3分経過した段階で、「大声で職員を怒鳴ることはやめてください」とあなたは患者に言います。
それでも大声で抗議を繰り返す場合は、カスハラにあたる可能性があるので、「大声で怒鳴られると職員が委縮して、何の対応もできなくなります」とはっきり伝えてください。
しかし、行為者が大声で怒鳴ることを止め冷静になられた場合は、苦情をお伺いすることが必要です。
その時は、当該職員ではなく他の人が聞くようにしてください。
その過程で、また大声を出す、あるいは不当な要求をした場合はカスハラにあたる可能性があります。