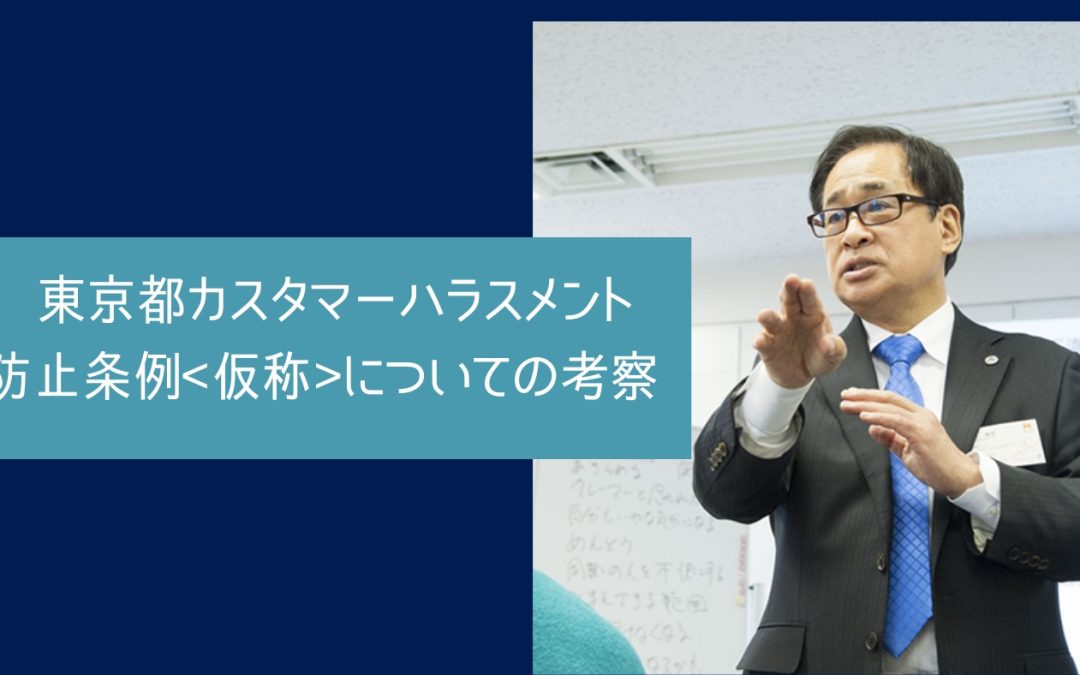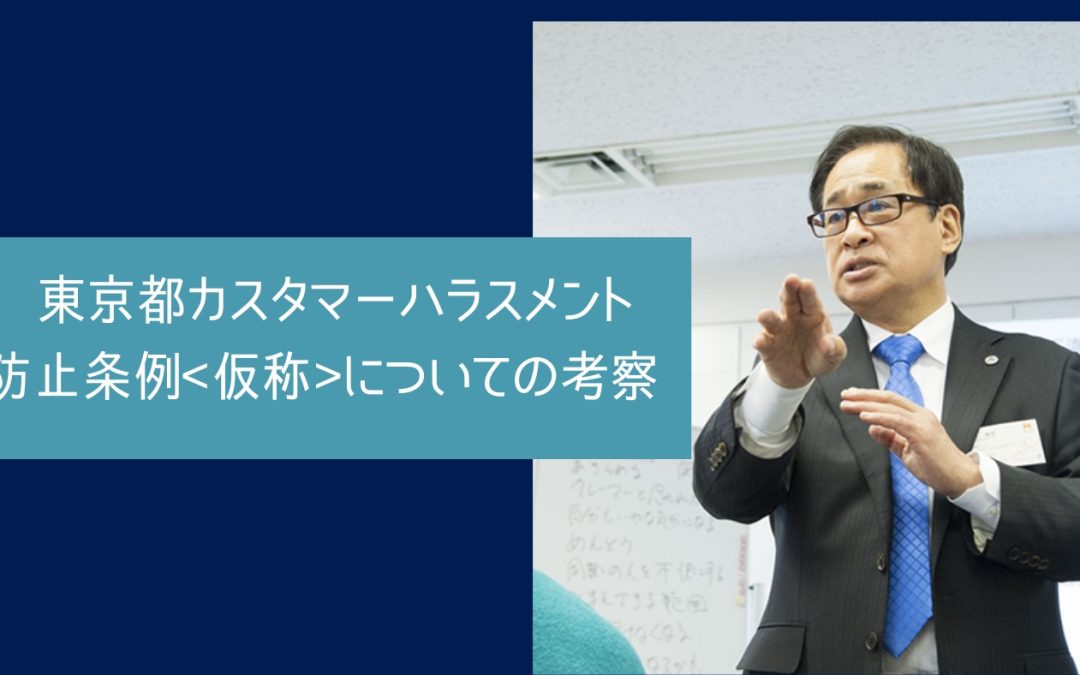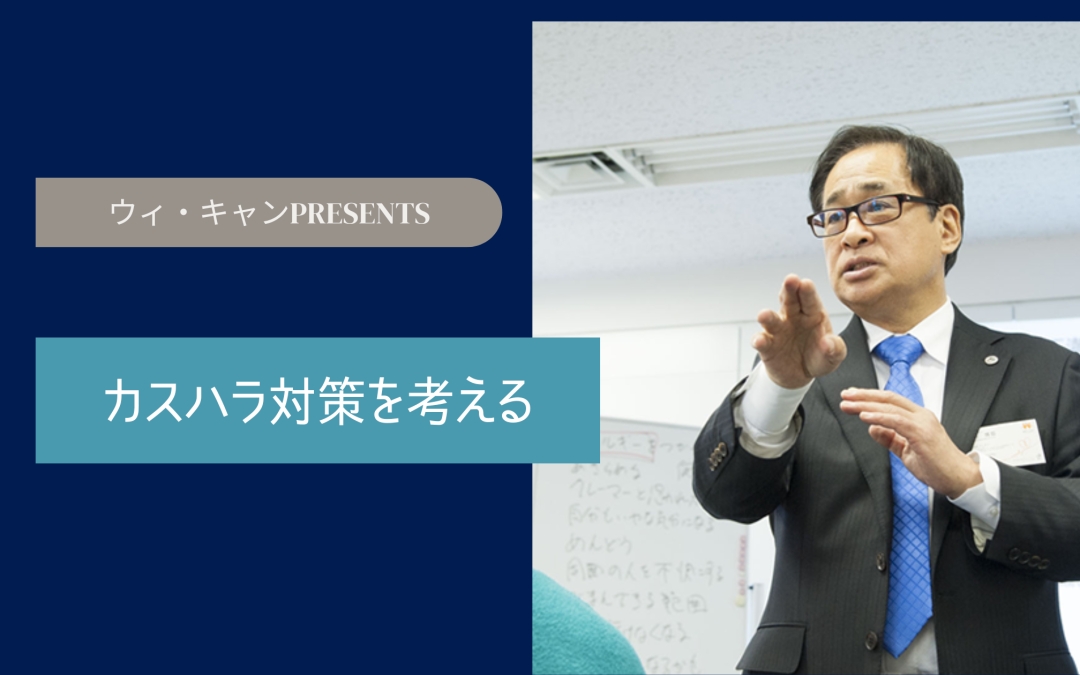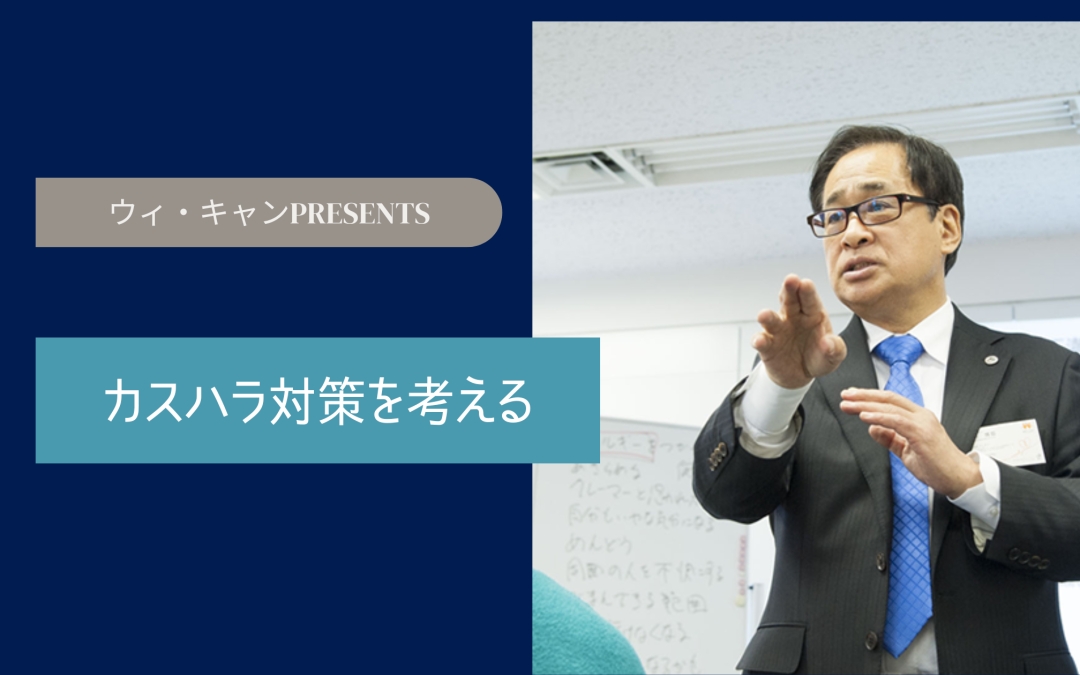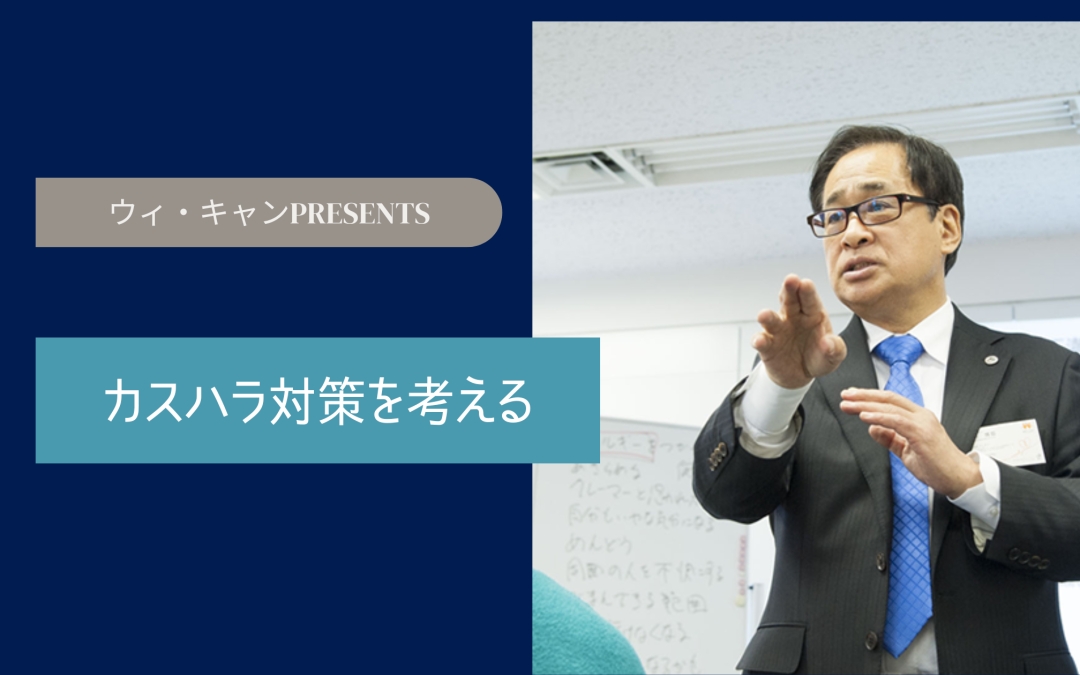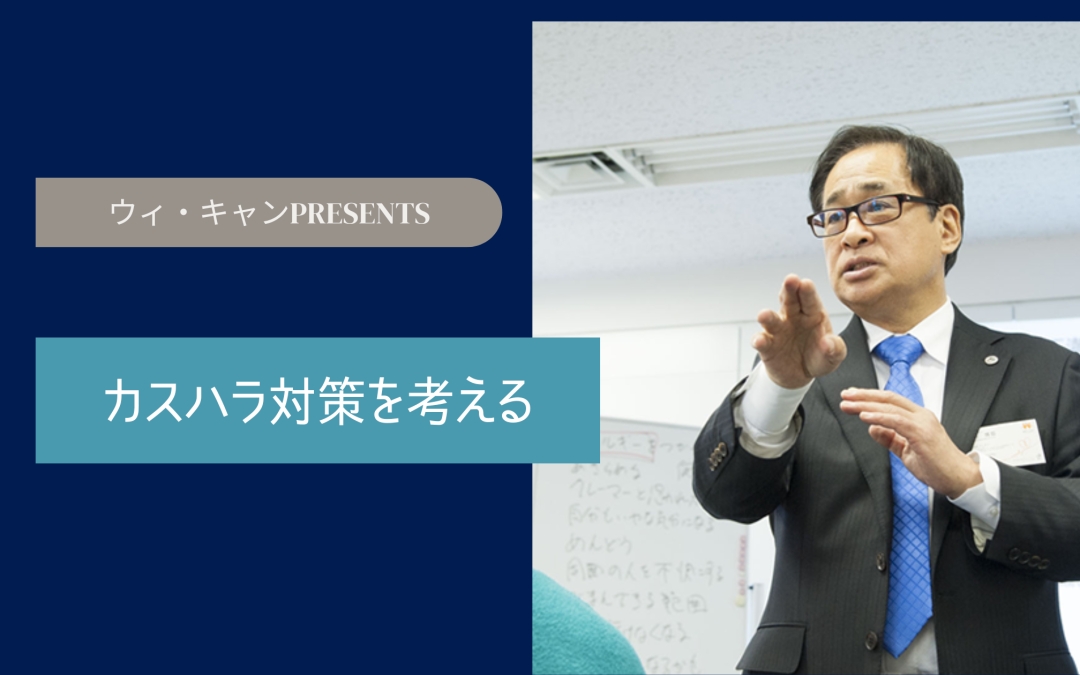執筆者 濱川 博招 | 2025年02月07日 | カスタマーハラスメント対策
2024年7月に東京都産業労働局から 「東京都カスタマーハラスメント防止条例<仮称>」について基本的な考え方が出されましたので、こちらについてご紹介したいと思います。 はじめに 本年7月に、東京都産業労働局から表題の基本的な考え方についての通達が出ました。 既に読まれている方もいらっしゃると思いますが、基本的な内容についてお知らせします。 1.策定の趣旨 ① 誰もが等しく豊かな消費生活を営み、働くすべての人が持てる力を存分に発揮し、事業者が事業活動を円滑に継続する社会を作り上げるために、...

執筆者 濱川 博招 | 2025年01月16日 | カスタマーハラスメント対策
情報共有の重要性 カスハラを防止するためには、医療者側だけでなく患者さんにも、情報を共有する必要があります。 患者さんの情報を共有するための方法 情報を共有する方法として、小冊子を作成して配布するのは、いかがでしょうか。以下は小冊子を作成する手順です。 手順1 医療機関として、「患者さんに対してどのような診療を提供したいか」を目標として作成します。 手順2 目標が作成できたら、その目標を達成するために、以下をそれぞれ列挙します。 「私たちが行動すること」 「患者さん家族へのお願い」...

執筆者 濱川 博招 | 2025年01月04日 | カスタマーハラスメント対策
患者・家族からの暴力を防ぐために 先月に引き続き、「患者・家族からの暴力を受けない」対策について考えます。「告知のためのポスターをどう活用するか」など、自治体や医師会が作成する資料を参考に取り組みを進めましょう。 ハラスメント行為の背景と認識 ハラスメントは本人の受け取り方に依存し、その認定は難しい場合があります。悪意のないクレームがエスカレートして暴言に発展するケースも多く、加害者自身がハラスメントと認識していないことが考えられます。 患者中心の医療提供とその課題...

執筆者 濱川 博招 | 2024年12月12日 | カスタマーハラスメント対策
先月号では、「カスタマーハラスメント」の病院の基準を作りました。その基準に基づいて、職員の対応やフォローはある程度できるようになると思います。 しかし、その基準を患者や家族に知らせなければ、効果はありません。患者・家族に知らせることが「ハラスメント被害を減少させる」第一歩と考えます。 そこで今回は、「ハラスメントの基準を公開する必要性」について考えていきます。...

執筆者 濱川 博招 | 2024年11月09日 | カスタマーハラスメント対策
先月号で「カスタマ-ハラスメント」には、明確な基準はないと申し上げました。厚生労働省の指針があるものの、ハラスメントは受ける人の感じ方により、ハラスメントと感じない人もいます。ひょっとすると、同じ人でもその時の気持ちで、感じ方が変わる可能性があります。...